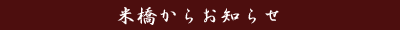
当店の簡単なご利用について
当店では十分吟味したそば粉を使用しております。
重要:お蕎麦は打ちたてをお出ししていますので、都合により新たに打たなくてはならない場合は約20分ほどお時間をいただいております。何卒ご了承願います。
- おすすめ天ざる
- :2,350円(税込)
- 目の前で揚げる天ぷら4点(エビ・イカ・野菜 / 野菜のみ可)
その後、石臼挽きの打ちそばへ続きます。 - セイロのみ
- :1,300円(税込)
- 温かい掛け
- :1,200円(税込)
- そばがき
- :800円(税込)
- 100%純粉 鍋がき
地元産 足柄茶を使っております。
酒類のご注文にはそば味噌の御通しが付いています。
一品ものは単品のみでは対応が難しく、伝承会席でのご検討をお願いします。

当店の感染対策について
当店では引き続き「マスクの着用」「手指消毒」「遮へい板」「強力な換気」「一組(1テーブル)4人または同居家族、2時間を目安」を行っていますのでご来店の際にはご協力をお願いします。特に換気には力を入れています。
三菱電機納入事例店主より一言
令和3年、おかげさまをもちまして「米橋」は創業50年という大きな節目を迎えることができました。世の中が大きく変化する中、それでも半世紀もの長い間営業を続けてこれたのは、ひとえに長年に渡りご愛顧いただいたお客様の温かいご支援の賜物と感謝しています。
「米橋」は、スタンド天ぷら店として近くのビルの地下8席のお店からスタートし、実直に職人路線を貫いてまいりました。 ここ30年は小田原の歴史を献立に組み込んだ「見立献立」という自慢のお値打ち献立を中心に、1組8名様からのご予約を1週間前のお申し付けで承っております。
多くの料理店が単に魚を一刀に惣菜にこしらえるのを立場(つけば)料理といいますが、当店の「見立献立」は昔あった、今でもあるという文献による綿密な裏付けや伝承による数々を味わいながら、深い知識もいただくことができるものです。
およそ6?8種のコースがあり、相模国小田原城城主の大森氏から明治の近代洋食を広めた村井弦斎までテーマを時代順に取り揃えております。
この献立・物語シリーズは、新たにこしらえては適宜お店の催事として実施しております。
案内をご希望の方は、宛先を募っております。
そんな大げさな注文は気がひけるという方には、大名コース(4,290円/税込)をお勧めします。
その日の会席が2-3品入りますので、その一端をご堪能いただけます。
より内容濃く仕上げられますので1時間以上前のご予約をお勧めします。
浅春の会席(6,600円/税込)

R6年3月中頃

真鶴 鰤 鎌倉おろしナマス

豆腐と鮭のパテ 白ソース レモン酢掛け
- 〇 グリーンマヨネーズ アスパラ・空豆
- ◦ イタリアパセリのマヨネーズソース
- 〇 そばがき 汁椀みそ仕立て
- ◦ そばがきは鶏そぼろ入り
- 〇 真鶴 鰤 鎌倉おろしナマス
- ◦ 大根おろしでいただく
- 〇 ロールキャベツ 和風スープ炊き
- 〇 豆腐と鮭のパテ 白ソース レモン酢掛け
- 〇 立場2品
- 立場(つけば)とは産地での調理
- ① 翻車魚 共醤油添え
- ◦ 身と肝は塩で〆て、湯引きする。身はスライス。肝はしっかり湯をして裏ごしし、酒・醤油・味醂と合わせ、仕上げに生姜汁を絞る。
- ② 槍烏賊 浜煮
- ◦ 槍烏賊は墨を取り生姜片を入れて当座煮にする。
- 〇 天麩羅・冷掛けそば
- 〇 水菓子
寒しのび 立春を望む頃(6,600円/税込)

R6年1月中頃
 前菜
前菜
 鯛 出汁のグラタン
鯛 出汁のグラタン
- 通し
- カキ豆腐(カキの肝のみを寄せた)
- 前菜
- 時計回り:小袖寿司(アジと鮭)、ばらん舟懐敷、陽向新筍(柚子味噌くら掛け)、合鴨ロース、 大福印元 節分盛り、黄梅花の魚カステラ
- 脇小鉢
- 三色煮豆(黒豆、大豆、金時)
- 吸物椀
- 清汁(うずら鳥のつくね、春菊、口・柚子)
- 料理なます
- 向枕:寒芹と固蕾茶花、なめり茸2種、沖縄もずく
前盛り:たこ、〆鯖、鮪、さわら、海老、ほたて
香草・伊パセリ、ロ・すだち、敷き酢 - 煮しめ
- あじ摘入、里芋、高野豆腐、焼麩、牛蒡、人参、椎茸、つまみ菜
- 焼皿
- 鯛 出汁のグラタン(鯛、しめじ茸)
- 天ぷら
- 自然薯磯辺巻き、海老、いか、鱚、舞茸、天つゆ
- 食事
- 手打ちそば柏南蛮、洗い葱(薬味)、七味
- 後菓子
- りんごの焼き菓子、地産いちご
現在から古を眺める会席(6,600円/税込)

- 箸始
- 胡麻豆腐禅宗仕立
- 饗応籠盛
- くず葉寿司、かんぜ玉子(能の観世模様)、鳥ミンチの松風焼き、酥(そ:日本のチーズ)、 紅葉人参
- 吸椀
- 集汁
- 年賀向けいか塩辛
- 甘鯛室町期杉板炙り
- 料理なます
- (永く続いた宴会の主品)はやと瓜、蕪、もずく、矢柄、鯛、たこ、金目、有頭海老、すだち、香草、敷三杯酢
- 煮しめ
- キスのつみれ(蒲鉾の材料)、八ツ頭、こうや豆腐、こんにゃく、人参、牛蒡、青菜
- 南蛮風油もの
- (衣の厚い天ぷら)海老、カキ、茸、油を切るための天つゆ
- 硯小鉢
- 黒豆とうずら豆煮
- 江戸夜鷹のそば
- 江戸時屋台のぶっかけそば(薬味・白葱、青葱)
- 茶菓子
- 大柿と羊羮
近隣にご宿泊の方への定食
お仕事等で宿泊施設にご滞在の方に定食をご用意しています。
3,000円(税込)お一人様から可
歴史をたべる
- 伝承会席
- :3,950円(税込) / お一人様から
- 汁(旅籠の汁椀)・ナマス類・煮物・焼物・油物・ぶっかけそば・後菓子を基にしております。
ご来店の30分前にでもご予約をいただけると、いっそう内容の濃い仕上げができますので、ぜひ事前のご予約をお願いします。
休会のお知らせ
これまで永くやってまいりました研究会形式の献立発表会(歴史サロン例会)をしばし休ませていただき次の機会について考えてみます。
何卒よろしくお願いいたします。
歴史サロン例会 会員募集中
これまで、史料に基づく郷土・歴史会席を発表してまいりました。 これらを、さらにわかりやすく整えて常会とします。
年に5から6回の予定で、10月1日(土)より初めます。
すでに5月3日に、氏康生誕500年「尚武会席」を行いましたが、こつんとまとまりご好評をいただきました。
7月9日にも同じ献立を講談師のグループにもお出ししました。
ご登録いただけると、その都度事前にお知らせします。
第1回は「奈良茶飯」
江戸、明暦の大火の直後に出した奈良茶飯セット(現代の定食)が大ヒットしました。それが今回の原形となります。それを、小田原風にしてお召し上がりいただきました。
第2回は「つばき油の天ぷらの会」
屋台から始まった、そば、すし、などから、なぜ天ぷらだけが現在専門店で敷居が高くなってしましたのかも明かしたいと考えます。
第3回は「尊徳の食事」
元・神奈川県立図書館資料部長 石井敬士氏の話(尊徳はお酒が好きだった)をまじえて、お召し上がりいただきました。
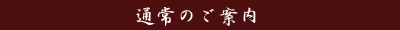
通常の季節の会席料理 ご接待、会食をお部屋にて。
お申し込みは当日でも結構ですが、出来るだけ前日までにご予約をお願いします。
お祝い事・ご法事・郷七・歴史・精進料理はご予約をいただいています。
2名様から10名様まで
料金は1名様につき 5,400円〜、法事は 4,400円〜(消費税込・サービス料別)
※特に郷土・歴史料理は8名様からですが、4名様以上で略式、応相談でご予約を承っています。
ご宴会向けセットをご用意させていただいています。
飲み放題ではありませんが、飲み物とお料理を合わせて5千円見当で、幹事様とご相談させていただきますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
カウンター席、テーブル席につきましては合わせて15席、月曜日〜土曜日夕方5時〜9時入店までで、お酒に合わせた色々なお好みの単品料理や、郷土・歴史にちなんだ料理の一部、また定食、手打ちそば、おにぎり、お茶漬け、他などお食事もご用意させていただきます。
【米橋料理店】
- 営業時間
- 昼11時30〜夜11時頃まで
- 定 休 日
- 火・水曜日
(但し、ご予約は定休日に関係なくお受け致します。) - 電 話
- 0465 22 4645
住 所:〒250-0011 小田原市栄町2-2-11
電 話:0465-22-4645
お 席:カウンター席+テーブル席(15名様まで)
お座敷(10名様まで)
当店では現在も新型コロナ感染拡大防止策として、一組(1テーブル)4人または同居家族、2時間を目安とさせていただいていますのでご来店の際にはご協力をお願いします。
内 容:季節のそぞろを取り入れ、個性品をご用意いたします。

-
■角長皿に■
- 魚付半ぺん
当時の半ぺんは、山芋と豆腐の精進物だった。
半日干しの魚につけたもの。 - 海雀(うみすずめ)魚せんべい
皮はぎのくずを打って蒸して干す。
丸くする縁起物。 - 金団
当時のきんとんは、甘い物を芯にして周りを囲んだもの。
-
貴重な贈答品 ごんぎり
干し鱧(はも)のこと。削って食材とした。 -
あいきょう
子持ち鮎の乾燥品 -
武将の塩辛
熟(な)しものと言った。
精白米でつくる。 -
中世のスシ 鰯の早馴れずし
玄米で漬けるのでさっぱりしている。
房州にかけての産品。
寒の食べもの。 -
醤油がない頃のさしみ 塩鯖
塩をして一週間くらいで塩が微かに発酵する。
煎り酒で食べる。
差ミと記す。
煎り酒を和えれば「なます」になる。
傍には栗を針打ちした栗生姜が添えられる。
色々な薬味が付くのも特徴。 -
本膳の要 湯漬け
茶漬けの類、湯・茶のほか煮貫(にぬき)といって味噌を溶いた出し汁を漉したのが武将好みと言われている。 -
香の物
傍に必ず付く。
三年物の漬け物を言う。
それより短い物を浅漬け・一夜漬けと呼ぶ。 - 見映え 雉の羽盛り(はもり)
この盛り方自体、昭和30年代始めまで各地であった。
雉は戦国武将の代表食材。 - 胡麻羹
ごまを摺って、本葛で寄せたもの。 - 高たんぱく源 江豚(イルカ)
後北条氏は伊豆の武士にイルカを納めさせていた。
小田原は食べる産地として。
江戸時代には字が海豚と変わる。
-
■筒割り■
- 秀吉の好物 牛蒡の味噌漬け
大根とともに日本だけの扱いと言われる。 - 鰯の辛煮
万葉の頃からの最強の保存食。
-
■三方盛り■出陣、帰陣の意味もある
- むかご串亀足
串は転けない。歓待を表す。 - 勝ち栗
栗を蒸して干したもの。 - 喜ろ昆布 昆布を揚げたもの。
-
■ひょうたん皿■
- ういろう
米粉を餅菓子にしたもの。

- 杉板門前焼き
赤身の杉板に挟んで焼く。
安全な食べ物。 - 旅人の塩辛
よく発酵させてある。 - 楚割(すわやり)
手のひら大の開き鰺を言う。
塩を打って朝日とともに干す。
頭まで開くのが小田原流。
塩が豊富にあったなごり。 - 楚割(すわやり)の炊き込みめし、冷めても持ち運んでも旨い。
- 竹管の羹
椎の実を粉挽きし蒸したもの。 - へしこ
そうだ鰹を糟に漬けて焙ったもの。